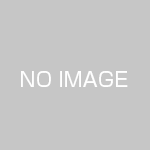M&A取引において「のれん代」は、会計上極めて重要な意味を持ちます。買い手側企業であれ売り手側企業であれ、正確に理解しておく必要があります。本稿では、M&Aの「のれん代」の計算方法のみならず、会計処理や注意点についても詳細に解説します。
M&Aにおける「のれん代」の意味
貸借対照表の固定資産には「のれん代」という勘定科目があります。「のれん代」とは、お店の暖簾(のれん)に由来する言葉ですが、会計上の「のれん代」はM&Aにおける実際の買収価格からの売り手側企業の純資産額(時価)を差し引いた価額のことです。具体的には、売り手側企業の純資産額(時価)が8億円だった際に買い手側企業が実際に10億円支払った場合には、のれん代は2億円(10億円 - 8億円)となります。
ビジネスは、有形資産(個別に明確な価値を有している財産)だけで収益を得ているわけではありません。有形財産に付加して無形資産(技術力やブランドなど個別の価値が明確ではない財産)もあり、有形・無形の各財産が一体的・連携的に活用されることでより大きい価値を発生させます。
例えば、時価10億円の工場用の土地・建物と、時価10億円の機械設備を利用して30億円の売上のあるビジネスの場合に、その土地・建物と機械設備は20億円で購入することは難しいでしょう。30億円の売上が生じているため、20億円よりも高額な値段で購入されることが一般的だと考えます。
土地・建物と機械設備(ビジネス)が30億円で売却できたのであれば、土地・建物や機械設備という有形財産の時価20億円の他に10億円の値が付いたということです。有形財産の時価を超過したM&Aの取引価格の分が「のれん代」です。なお、有形財産の時価純資産価額がマイナス(債務超過)のケースであっても、マイナスのままで計算するため、結果としてM&Aの取引価格よりものれん代が高くなることはあります。
のれん代に留意すべきフェーズ
のれん代に留意が必要なのは、買い手側企業が売り手側企業の価値を調査・評価するデューデリジェンスのフェーズになります。買い手側企業は、デューデリジェンスで売り手側企業の価値やリスクをさまざまな側面から調査・評価しますが、有形資産だけではなく無形資産についてもしっかりとデューデリジェンスを実施することが必要です。
のれん代へと繋がる無形資産には、知的財産権(特許権や意匠権など)、顧客ネットワーク、技術開発力などが挙げられます。これらは売り手側企業に内在しているものですが、M&Aなどの場合でなければ自社で評価する必要はありません。M&Aで実際に会社を買う場合に、買い手側企業がしっかりと調査・評価することになるのです。
事業、財務・税務、法務、人事・労務、ITなどのデューデリジェンスは、ある程度客観的に調査・評価することが可能ですが、のれん代に関係する項目に対するデューデリジェンスにはどのような特色があるのでしょうか。知的財産に対するデューデリジェンスは、これまで正確な価値を測定する基準が確立されていた訳ではなかったため、ようやく特許庁がGitHub(プログラムコードなどの保存や公開が可能なソースコード)管理サービスを活用した知的財産のデューデリジェンスに関して標準手順書の策定が進められています。
また、顧客ネットワークに対するデューデリジェンスはどのような顧客基盤を有していて、収益力の向上に貢献しているのか否かなどを調査・評価します。そして、技術開発力に対するデューデリジェンスは、どういった人材が技術・開発に携わっているのか、競合他社と比べて優位な材料はどういった点かなどを詳しく調査・評価します。
関連記事:デューデリジェンス(DD)とは?意味からM&Aにおける必要性と実務上のポイントまで完全理解
のれんの償却期間について
日本の会計基準においてのれん代は固定資産に計上した後に費用として償却されるルールとなっています。ただし、一度に償却費用を計上してしまうと、買い手側企業の利益が大きく減少します。そのような状況を回避するために、毎年のれん代を少額に分割して資産計上する「のれん代の償却」という方法が採用されることが一般的です。
しかし、何十年もの長期間もわたって細分化して償却することは許されておらず、最大でも20年以内で計上した全てののれん代は償却することが必要です。のれん代の償却費用を計上すれば毎年費用が増加します。したがって、のれん代を減損するケースでは、費用が一時的に増加しますが、翌年度以降における償却の費用は減少します。
具体例を挙げると、ある事業の純資産が20億円だったものを30億円で事業買収した際にはのれん代は10億円(30億円 - 20億円)となります。のれん代10億円を10年間で償却する場合には、各年で1億円ずつの償却額になります。
他方、IFRS(International Financial Reporting Standards、国際財務報告基準)や米国会計基準においてはわが国と異なりのれん代の償却は許されていません。元来は償却を認めていたのですが、合理的な方法でのれん代の耐用年数を見積もることは簡単ではない、という理由から現状ではのれん代は非償却対象資産となっています。のれんの価値が大きく下がった場合にのみ減損テストを実施して減損処理(まとめて損失を処理する方法)をします。
のれん代の会計処理について
既に説明したように、M&Aにおける実際の買収価格からの売り手側企業の純資産額(時価)を差し引いた価額がのれん代のため、本来の売り手側企業の企業価値よりも高い金額で買い手側企業が買収したということになります(のれん代がプラスの場合)。実際にM&Aでは、売り手側企業は会社を高く売りたいためさまざまな付加価値を付けようとすることが一般的です。具体的には、自社のブランド力、強固な顧客基盤、競合他社よりも秀でている人的リソースといった無形資産に関する優秀さや力強さを買い手側企業に主張し売却する額をアップしようと試みます。
基本的には、売却額がアップすればするほど比例してのれん代もアップします。のれん代のアップは買い手側企業にはより支払額が増加することにはなるのですが、自社の貸借対照表には無形資産として計上されるため何ら実損が生じるということではないです。具体的には、無形資産のひとつであるブランド力は将来的にも収益が発生することに繋がる企業にとっての大きな武器となります。一時的に出費の増大になりますが、その出費額に相応しいリターンを期待することができるでしょう。つまり、そうした出費は将来にわたる収益力を得る目的でのれん代を前払いしているとも言えます。
M&Aで生じたのれんは、資産に計上されるので仕訳処理が必要になります。例として、純資産額1億円(内訳:資産3億円、負債2億円)の企業1億5千万円で買収したケースでは、5千万円ののれんが生じるので、下記のような仕訳となります。
| 借方 | 貸方 | ||
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 資産 | 3億円 | 負債 | 2億円 |
のれん |
5千万円 | 当座預金 | 1億5千万円 |
のれんは、永続的に資産としての価値を保持するような勘定科目ではありません。したがって、時間の経過と平仄を合わせて費用計上(償却)をする会計処理が必要になります。この会計処理は、前述したように、日本基準と国際会計基準・米国基準という会計基準によって違いがあります。
日本基準では、のれんは20年以内に償却するというルールが定められています。実際の償却期間は、そののれんがどのくらいの期間影響を及ぼし続けるのかという観点から検討され設定されます。一般的には、投資回収期間を考慮し設定されるケースが多いようです。例えば、ビジネスサイクルが長期間で安定している製造業では10年以上の期間で償却し、反対に技術の進化と衰退による移り変わりが激しいIT業では数年間で償却することが多いです。
一方、国際会計基準や米国基準ではのれんの償却は認められていません。その代わりとして、年に1度の減損テストの実施が必要になり、その結果大きな価値の減少が判明した場合には減損処理します。
のれん代で注意すべきこと
既に説明したように、会計基準の違いによってのれん代の償却に関する考え方も異なっていると説明しましたが、日本基準であっても減損処理が発生しないわけではありません。M&Aで会社や事業を買収した後に、不祥事や業績不振などの理由でのれん代を回収することが難しくなってしまうようなケースも実際に発生しています。
このような場合には、買い手側企業で計上されたのれん代の価値が大きく減少してしまうか、場合によっては価値がなくなってしまう可能性も考えられます。回収可能額をよく考えたうえでのれん代の計上金額(簿価)と比べて、大きな金額の乖離が生じた場合には計上されているのれん代を見直す必要が生じます。この乖離が生じた分に相当する損失金額の処理がのれん代の減損処理です。
言い換えると、のれん代の減損処理とは会計上のれん代の減損対象となる金額を一度にまとめて費用として取り扱う会計処理です。ただし、のれん代の減損処理は以前から日本で発生したものではないです。会社法が2006年に改正されて以降、活発にM&Aが行われるようになり、大規模なM&A取引や巨額なのれん代の発生などにより、のれん代を大きな規模で減損しなければならない事態が生じるようになりました。
例として、のれん代が1,000億円で買収した企業が不祥事の発生によって、大きく企業イメージを悪化させた場合に、買収時に予想していた収益を獲得することが難しいとわかったとしましょう。こうしたケースでは、のれん代の減損処理を実施することが必要になります。
企業イメージの悪化により収益性が大きく低下した会社の企業価値や投資回収を確認するとともに、それらをのれん代の1,000億円と比べたうえで、減損を実施するか否か、減損処理を実施する金額なども検討しなければなりません。どのくらいの金額の減損処理を実施するのかに関しては算定しにくいため、監査法人、公認会計士などのプロフェショナルな専門家の協力を得る必要があるでしょう。このような算定のことを、減損テストと呼んでいます。
のれん代に関して注意が必要な点は、上記の減損処理の他にも会計上と税務上の取り扱いが異なっているという点も挙げることができます。株式譲渡によるM&Aで連結貸借対照表を作成する場合には、税務上ではのれん代が発生することはありません。ただし、事業譲渡、あるいは現金を対価とする吸収分割の場合には、のれん代は税務上資産調整勘定あるいは差額負債調整勘定という勘定科目として発生します。
他方で、会計上は現実の買収額から純資産額を差し引いた差額はのれん代として計上されますが、のれん代を毎年一定の金額ずつ償却し、仕訳上では借方に記載することになります。一般的には、売り手側企業の純資産額よりも実際の買収額の方が多額になるケースが多く、プラスののれん代になるでしょう。しかし、いわゆる「負ののれん代」の場合には、買収金額よりも資産額の方が多額になるケースもあります。この場合には、買収額よりも差額が大きな金額になるケースが考えられます。つまり、のれん代がマイナスになり得るのです。こうしたケースでは、差額ののれん代を一括で利益として貸方に記載することになります。
のれん代の計算方法は大きく分けて3種類
のれん代を算定する方法には、DCF法、マルチプル法、年買法の3種類の方法があります。
DCF法
DCF(Discounted Cash Flow)法は、事業計画などに基づいて会社の将来フリーキャッシュフローを計算して、その計算値を現在価値へと修正して株価を求める方法です。したがって、DCF法の算式は将来に獲得できると予想したキャッシュフローに割引率を掛けます。起業したばかりの企業や実績に乏しいベンチャー企業などにとっては、有用な計算方法です。DCF法の計算に多大な影響を与える要素は、将来キャッシュフローと割引率の2つになります。
フリーキャッシュフロー(FCF)とは自由に会社が使うことが可能な資金のことで、原則として、フリーキャシュフローの中から借入金に対する返済をしたり株主に配当を実施したり事業の拡大を目的に設備投資を実施したりします。もし、フリーキャッシュフローがマイナスだった場合には、会社を維持・継続するために金融機関から融資を受けたり第三者割当増資を実施したり、資産を売却するなどして資金を調達する必要があります。
割引率とは、原則として時間の経過とともに資金の価値は増加するという考え方に基づくもので、一般的には加重平均資本コスト(WACC、Weighted Average Cost of Capital)という、負債(借入金や社債の発行費用など)のコストと資本調達(増資など)のコストを加重平均したものを用います。
マルチプル法
マルチプル法とは、売り手側企業と類似している上場企業であれば同じような企業価値、あるいは株式価値を有しているという考え方に基づいている評価方法です。つまり、いくつかのよく似ている上場企業を選定したうえで、それぞれの上場企業の株価をベースにした事業価値を簡単な算式に代入してその平均値などを求める方法になります。
マルチプル法には定まった計算方法があるわけではないですが、一般的には、EBITDA(税引前利益+支払利息+減価償却費)倍率、売上高倍率、営業利益倍率、株価収益率(PER)、株価純資産倍率(PBR)といった指標を用いて算定されるケースが多いようです。
マルチプル法を利用する場合には、以下のような点に留意しましょう。
- 選定された上場企業が妥当なのか
- 選定された上場企業の株価には異常な値動きはなかったか
- どの倍率(指標)を使用するべきか
- 上場企業と売り手側企業に関して正確な財務情報を収集できるか
関連記事:EBITとEBITDA 2つの違い、営業利益との違いやメリット・注意点を徹底解説
関連記事:EBITDAの計算方法・評価方法とM&Aの時に活用するポイントを徹底解説
年買法
年買法とは、会社の純資産価額(時価)に営業権(年間利益額)のX倍(一般的には、1倍~5倍くらい)の金額をプラスして売り手側企業の価値を求める方法です。つまり、営業利益 × X年分 + 純資産価額という算式で計算されます。年買法の利点は簡単に計算できることと理解し易いところです。したがって、中サイズあるいは小サイズのM&A取引の案件においてはよく利用されています。
実際には、上記の3つの方法以外にもさまざまな計算方法があります。また、上記の3つの計算方法を複数利用して、その平均値を採用するようなケースも考えられます。
関連記事:企業価値とは?時価総額や事業価値との違いや算出方法をわかりやすく解説
のれん代をアップさせる売り手側企業の3つのコツ
高く売るコツ1.自社を高く評価してくれる買い手に売り込む
のれん代は、買い手側企業の主観によって決定されると言っても過言ではありません。したがって、のれん代を高く評価される可能性の高い買い手側企業を見つけることがのれん代アップに繋がります。売り手側企業が保有している技術開発力、ノウハウ、顧客基盤と販売網などを入手したいと考えている企業、M&Aを活用して費用を削減と売上の増加を果たしたい企業、売り手側企業のビジネスとシナジー効果が高い(買い手側の)企業はのれん代を高く評価する可能性が高いです。
買い手側企業にすれば、全てを自社の力で新たなビジネスを起こすよりも、既に当該ビジネスを運営している売り手側企業を買収したほうが遥かに効率的でしょう。また、売り手側が構築している販売ネットワークを入手できることもM&Aの大きな魅力だとも言えます。
売り手側企業も買い手側企業も、自社が希望している価格や条件に近い内容を提示しているような相手先を探索するのであれば、M&A仲介会社が運営しているマッチング・サイト上に公開・掲示されているので、こうしたM&Aマッチングサイトに登録して交渉する相手を見つける方法も効率的でしょう。
高く売るコツ2.買い手に「欲しくなるような情報」を与える
基本的には、買い手側企業は売り手側企業のことは全く知らないと考えておいた方がよいでしょう。買い手側企業に前向きな姿勢で検討してもらうためには、正確かつ具体的な情報をオープンにして、会社の魅力を適切に伝える努力を実行・継続していくことが極めて重要です。不明確でわかりにくいような情報を公開されても、買い手側企業は不安になってしまうでしょう。
買い手側企業に、決算書や財務諸表などを見てもらうことは当たり前ではありますが、それだけでは十分ではありません。売り手側企業にどのような魅力や強みがあって、もし買収した場合にはどのようなメリットを得ることができるのかといった点を心底から理解できない場合は、買い手側企業は決して購入しようとは思わないでしょう。具体的な手続きとしては、IM(Information Memorandum、企業概要書)を作成して、買い手側企業に正確かつ具体的な情報を開示します。このIMは、M&A仲介会社やFAに作成を依頼することが可能です。
高く売るコツ3.買い手候補同士を競わせて「争奪戦」を巻き起こす
のれん代をアップさせるためには、買い手企業を入札によって決定する方法もあります。買い手側企業同士を競合させない限りは、高い買収価格を望むことは難しいでしょう。売り手側企業を買収する気持ちが高じた買い手側企業は、多少割高の場合でも是非買収したいと考える一方で、もし買収できるのであればなるべく安く買収したいとも考えているはずです。
したがって、個別の(1対1の)交渉の場面においては、さまざまな手を駆使して買収価格を安くすることを間違いなく狙いにきます。中小企業のM&Aでは一般的に、初心者の売り手側企業と老練な経験者である買い手側企業との交渉になるケースが多いので、売り手側企業が圧倒的に不利な状況に置かれます。
売り手側企業が不利な状態であっても高い買収価格を引き出すためには、入札による方法で複数の買い手側企業を競争させることが必要です。入札による複数の買い手側企業間の競争となると、買い手側企業は他の競合している入札者を意識する必要が生じます。ここで、入札で負ければ買収ができなくなるし、そうなる状況は回避したいと思わせることができれば、必ず満足できる入札価格を提示してくるでしょう。
事業買収/売却ならJPMergers
知識に自信がない、徹底したサポートを受けたいという場合は、JPMergersにご連絡ください。着手金や中間報酬はいただきません。国内最大級のM&Aアドバイザーバンクから、企業それぞれの特色に合わせた最適な人材を紹介させていただきます。
ただ単に契約を「成立」させるのではなく、双方にとっての「成功」を目指すJPMergersに、M&Aに関する悩みや不安をぜひお聞かせください。